About the Department電気電子工学分野の紹介
電気電子工学分野の紹介
コース概要
電気電子工学は、現代のあらゆる産業や社会生活の基盤として、不可欠な科学技術となっています。携帯電話、テレビ、デジタルカメラ、パソコン、インターネット、エアコン、自動車など、日常的に使用するあらゆるものは電気電子工学の高い技術によって支えられ、私たち人類の生活を豊かで快適なものにしています。
ユビキタス社会を支えるフォトエレクトロニクスや情報通信技術、電気エネルギーを作り出す発電技術、工業生産を支えるロボットの制御技術のほか、地球温暖化を防止するための太陽光発電やプラズマ応用環境対策技術、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなど、21世紀における人類の持続的繁栄のために必要な「人と地球に優しい革新的な未来技術の創出」には、電気電子工学の知識と技術を中核とした最先端科学技術の発展が不可欠です。
本コースでは、電気電子工学の基礎から応用に至るまでの体系的な教育に加えて、学生実験や卒業研究などを通した実践的な教育を行うことで、電気電子工学の専門的知識と技術を有し、社会で活躍できる人材の育成を行っています。
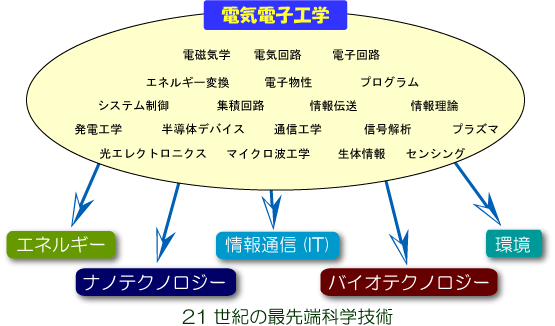
学習内容
電気や電子の振る舞いを利用して製品や産業に応用していくためには、その根本となる原理や法則をしっかり理解する必要があります。そのためには高度な数学や物理を修得することが不可欠で、その後、電気電子工学の基礎となる電気回路、電磁気学、電子回路などの専門科目を学びます。代表的な科目をいくつか紹介します。
基礎となる科目
高校より高度な数学や物理を学びます。
具体的には、微分積分学、線形代数学、微分方程式、複素関数論などです。
専門科目
電気電子工学の基礎となる科目から、それらを応用する知識・技術を修得するための科目が幅広くあります。
- 基礎科目
電気回路、電子回路、電磁気学、電気電子工学共通実験 - より専門的な科目
論理回路、信号解析論、電子物性論、情報通信工学、半導体デバイス工学、プログラミング論、環境電気工学など
沿革
| 昭和41年(1966) | 理工学部の設置、電気工学科の設置 (電気基礎学、電力工学、電気機器、電子工学) |
| 昭和48年(1973) | 電子工学科の設置 (電子基礎工学、通信工学、制御工学、電子応用工学) |
| 昭和50年(1975) | 大学院工学研究科(修士課程)設置、電気工学専攻の設置 |
| 昭和51年(1976) | 電子工学→制御工学、制御工学→情報回路工学に変更 |
| 昭和52年(1977) | 電子工学専攻の設置 |
| 昭和58年(1983) | 大学院工学研究科を大学院理工学研究科に名称変更 |
| 平成元年(1989) | 大学院理工学研究科を改組し、大学院工学系研究科(博士課程)設置 |
| 平成4年(1992) | 電子工学科に電子情報工学講座増設 |
| 平成9年(1997) | 電気工学科、電子工学科を改組し、電気電子工学科設置 (電子システム工学、知能計測制御工学、 電子情報工学、情報通信工学) |
| 平成10年(1998) | ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)設置 独立専攻の生体機能システム制御工学専攻の設置 |
| 平成12年(2000) | ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)、理工学部研究棟竣工 編入学生の定員化による助教授ポスト1名増 |
| 平成13年(2001) | 電気工学専攻、電子工学専攻を改組し、電気電子工学専攻設置 シンクロトロン光応用研究センター設置(学内措置) |
| 平成15年(2003) | シンクロトロン光応用研究センター設置(省令化) |
| 平成16年(2004) | 国立大学法人佐賀大学設置 |
| 平成31年(2019) | 電気電子工学科を改組し、 理工学科電気エネルギー工学コース・電子デバイス工学コース新設 工学系研究科電気電子工学専攻を改組し、 理工学研究科理工学専攻電気電子工学コース新設 |


